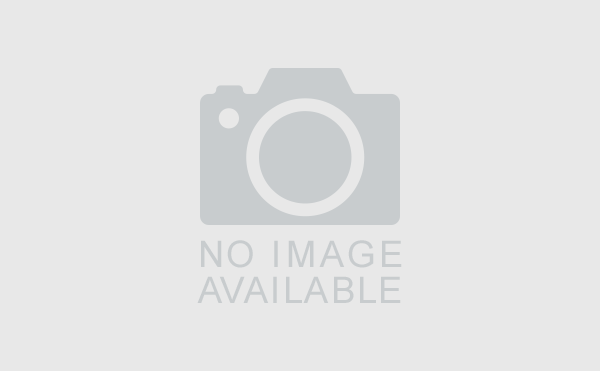【実体験あり】すき家のネズミ混入事件から考える、飲食店の衛生管理のリアル
2025年3月、ある衝撃的なニュースがSNSを駆け巡りました。
鳥取県にある「すき家 南吉方店」で、なんと味噌汁の中にネズミの死骸が混入していたという事件です。
このニュースを見て、驚きと同時に「やっぱりな…」という妙な納得感を覚えたのは、もしかしたら僕だけではないかもしれません。
なぜなら、僕自身も大学2年の頃、とある大手とんかつチェーンでアルバイトをしていた時に、目の当たりにした衛生環境があまりにひどかったからです。
今回は、すき家の事件を通して見えてくる飲食チェーンの衛生管理の実態、そして僕自身のバイト体験を交えながら、「現場のリアル」を皆さんと共有したいと思います。
すき家の事件概要:ネズミが“たまかけ朝食”に…
事件が起きたのは2025年1月21日午前8時頃。鳥取県のすき家・南吉方店で提供された「たまかけ朝食」の味噌汁の中にネズミの死骸が混入していたのです。

※実際の写真
この問題が明らかになったのは、被害に遭った顧客がGoogleマップに画像付きで投稿したことがきっかけでした。
ネット上では「AI画像では?」「フェイクでは?」という声もありましたが、すき家が後日、事実であることを認めるリリースを発表しました。
企業側の説明によれば、味噌汁の具材を複数杯分まとめて準備する過程で、1つの椀にネズミが混入。
さらに、提供前の目視確認を怠ったため、そのまま客に出されてしまったとのことです。
すき家はすぐに店舗を一時閉店し、衛生検査や施設の修繕を実施。保健所にも報告の上、2日後に営業再開しました。
また、全国の店舗に対しても「目視確認の徹底」を指示したとしています。
なぜ批判が殺到したのか?問題は“2ヶ月の非公表”
すき家への批判が特に強まったのは、この事件が約2ヶ月間も非公表だったという事実が明らかになったからです。最初に公になったのは、3月22日。「NEWSポストセブン」の取材により発覚し、ようやく企業側もリリースを出す形になりました。
この対応の遅さにSNSやメディアでは、
「もっと早く知らせるべきだった」
「他の店舗でも同じことが起きてるのでは?」
「隠蔽体質では?」
といった声が多く上がりました。
事実、2024年には大手製パン会社や学校給食でもネズミ混入が発覚しており、飲食業界全体に「衛生管理の再徹底」が求められているのが現状です。
アルバイト経験から見る“衛生管理の甘さ”
実は大学2年の頃、私はある大手とんかつチェーン店で半年ほどアルバイトをしていました。
全国展開している有名ブランドで、誰もが一度は見かけたことがあるような店舗です。
外から見れば清潔感のある店舗で、忙しい時間帯でも効率よく料理が提供され、安心して食事ができる――そんな印象を持っていた人が多いと思います。
でも、実際に厨房の中に入ってみると、その印象は大きく覆されました。
厨房の裏側で目にしたのは、衛生管理の甘さや、忙しさに追われる中での“見て見ぬふり”の積み重ね。
最初は「えっ、これ大丈夫なの?」と驚くことの連続でしたが、次第にそれが“当たり前”として処理されていく現場の空気に、どこか恐怖すら感じていました。
正直に言って、「これで本当に営業していいのか…?」と不安になるレベル。
ですが、当時の自分は学生バイトの一員として、見て見ぬふりをしていた部分もあったと思います。
これからお話しするのは、そんな私が実際に体験した飲食チェーン店の厨房での衛生管理の実態です。
おそらく、消費者として来店するだけでは見えない“リアル”がここにあります。
衛生研修は形だけ
最初の研修こそ、それなりにしっかりしていました。パソコンを使って、衛生管理や接客マナーに関する動画を見ながら学習する時間が設けられていて、「なるほど、ちゃんと教育体制があるんだな」と当初は感心したのを覚えています。
動画の中では、手洗いの手順や器具の消毒方法、異物混入を防ぐための注意点などが丁寧に解説されており、「飲食業界は衛生に厳しい世界だ」と、こちらも自然と身が引き締まりました。
しかし、実際に店舗に立ってみると、その意識はあっという間に崩れ去りました。
現場では社員も店長も常に忙しそうに動き回っており、ゆっくりと新入りに衛生管理を教えている余裕などまったくないのです。
食事時のピークには注文が次々と入り、調理場もホールもてんてこまい。結果的に、最初のうちは何が正しくて何がNGなのかもよく分からないまま、先輩バイトの動きを“見て真似する”しかありませんでした。
とはいえ、先輩たちもまた忙しく、個別に教えてくれるわけでもなく、わからないことがあっても「見ればわかるでしょ」「慣れればできるよ」といった空気が支配的でした。
“研修”と“現場の実態”との間には大きなギャップがあり、そこを埋めるフォロー体制もほとんどなかったのが正直なところです。
学生バイト任せの現場
多くの仕事は、実際のところ学生アルバイトによって回っている状態でした。
キッチンもホールも、現場の中心にいるのは大学生や専門学生などの若いバイトたち。
もちろん、中には責任感を持って真面目に働いている人もいましたが、全体としては個人の意識の差が大きく、衛生に対する考え方もバラバラでした。
「とりあえず回せばいい」「バレなきゃOK」という空気が、忙しい時間帯には特に強くなっていきます。
たとえば、本来は業務に入る前や食材に触る前には手洗いを徹底することが基本ですが、現実には手を洗わずにそのまま調理に入る人も少なくありませんでした。
というのも、ピーク時はとにかく時間との勝負で、手洗いに行く数十秒さえ惜しいと感じる空気があるんですよね。。。
また、清掃作業を終えた後に手を洗わず、そのまま調理作業に移る人も普通にいました。
ゴミ箱やモップに触った手で、とんかつを触ったり、盛り付け用のキャベツを扱ったり…。
誰かが注意するわけでもなく、“見て見ぬふり”が当たり前になっている空気がありました。
最も衝撃的だったのは、汚れた床に落ちたとんかつを「油で揚げるから殺菌される」と言って再利用していたことです。
本来であれば廃棄すべきものですが、忙しい時やロスを嫌う雰囲気の中では、平然とそれが繰り返されていました。
調理場の床には油や食材カスがこびりついていて決して清潔とは言えないのに、「火を通すから大丈夫でしょ」という、なんとも乱暴な理屈で正当化されていたのです。
食器もまともに洗えていない
特に衝撃だったのは、人手不足による皿洗いのクオリティの低さです。
飲食店において「食器がきれいであること」は最低限の前提だと思っていましたが、現場ではその“当たり前”がいとも簡単に崩れていました。
特に気になったのが味噌汁用のお椀。今回のすき家の事件と同じです。。
僕がいた店舗では、あらかじめわかめを入れておいて、注文が入ったらポットのお湯を注ぐだけで提供するスタイルを取っていました。確かに効率的ではあるのですが、そのお椀を大量に重ねて保管するため、底の汚れが付着しやすくなっていたのです。
しかも、その汚れた底が、次のお椀の中と直接触れてしまう構造上、知らず知らずのうちに内側にも汚れが移ることがありました。衛生的に見ても明らかに問題がある状態なのに、現場ではそれに気づいても、暗黙の了解でだれも不満は言いません。
一つひとつは小さな見落としでも、積み重なれば大きな問題につながる。
そのことを、当時の自分も薄々分かっていながら、忙しさに流されていたという後悔があります。
なぜこうした問題が起きるのか?
現場で実際に働いていた立場から強く感じたのは、こうした衛生問題の背景には、いくつかの根本的な要因が存在しているということです。
単に「誰かがズボラだった」「一部の店舗の問題」では済まされない、構造的な課題がそこには横たわっていました。
人手不足:とにかく忙しく、洗い物や掃除まで手が回らない
まず第一に挙げられるのが、慢性的な人手不足です。飲食業界は常にアルバイトの確保に苦しんでおり、ギリギリの人数で回している店舗も少なくありません。
ピークタイムになると、ホール・キッチン・洗い場のすべてが同時に忙しくなり、洗い物や掃除といった「見えない作業」にまで手が回らなくなるのが実情です。
「とにかく回す」「提供を止めないことが最優先」という雰囲気の中で、衛生面への配慮はどうしても後回しになりがちです。
どんなに衛生意識が高い人でも、体力的・時間的に限界がくれば「今だけは仕方ない」と判断せざるを得ない状況が生まれてしまうのです。
マニュアル重視で現場教育がない:形式だけの研修で実態が伴っていない
一応、入店時にはパソコンを使ったマニュアル研修が用意されています。
衛生管理や接客の基本については、そこそこ丁寧に説明されているのですが、実際の現場に出てみると、その内容がほとんど活かされていないことに気づきます。
というのも、現場には“教育の時間”がほとんど存在しません。
社員や店長は常に忙しく、バイトに細かく教えている余裕がないのが現実。
結局、未経験の新人が現場に放り込まれ、周りを見て覚えるしかない状態になってしまうのです。
結果として、研修は研修、現場は現場というように、教育と実務が完全に分断されてしまっているのです。
安さと効率が最優先:コストカットが優先され、安全や清潔さが後回し
飲食チェーンは、企業努力によって低価格を実現し、多くの人にサービスを提供しています。
しかしその一方で、「コストカット」が最優先される現場の現実があります。
とにかく安く、早く、効率的に回すことが求められ、衛生面への投資や人材教育は後回しにされがちです。
本来であれば、使い捨て手袋の交換やこまめな手洗い、床や調理器具の消毒など、細かな対応が必要ですが、それらを徹底するには時間もお金もかかる。結果として、ギリギリのラインで“なんとか回っている”だけの状態が常態化してしまっています。
アルバイトに任せきり:社員が多忙で、現場指導がほとんどない
そしてもう一つ大きな問題が、アルバイトへの過剰な依存です。
私が働いていた店舗でも、現場の半分以上が学生バイトで構成されており、社員は数名しかいませんでした。
その社員たちも、発注・シフト作成・クレーム対応・本部とのやり取りなどに追われており、現場に立ってバイトを直接指導する時間はほとんどありませんでした。結果として、新人同士で教え合う“自己流の教育”が横行し、ルールや衛生基準のブレがどんどん広がっていくという悪循環に陥っていたのです。
おわりに:信じすぎない目と、働く側の声を
今回の件で、あらためて僕たち消費者は「チェーン店だから安心」という幻想を少し疑うべきかもしれません。
そして、アルバイトなど“現場で働く人間の声”にも耳を傾けてほしいと思います。
もちろん、すべての店舗が衛生的に問題を抱えているわけではないし、真剣に取り組んでいるところもあります。
ただ、現場のリアルは案外、知られていないだけで厳しいのが現状です。
もし、あなたが飲食バイトをしているなら。
「自分は見て見ぬふりをしていないか?」と、一度問いかけてみるのもいいかもしれません。
※この記事は筆者の実体験と報道内容をもとに執筆しています。店舗や企業を非難することが目的ではなく、飲食業界全体への問題提起を意図しています。