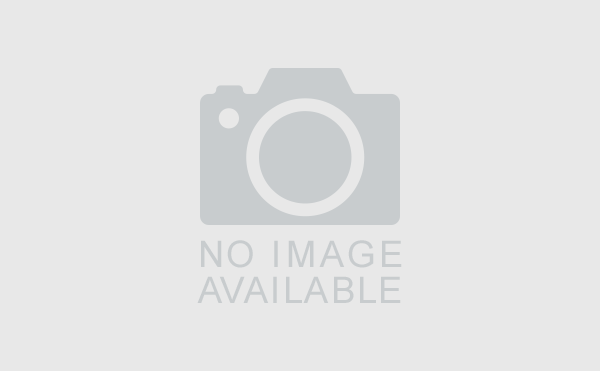人と比較してしまう癖との向き合い方|劣等感から自由になるためにできること

はじめに
僕自身、人と比べてしまう癖にずっと悩んできました。
それは大学に入ってから始まったわけではなく、もっと前、受験勉強の時期からすでに根を張っていたものです。
もともと人とのコミュニケーションが得意ではなかった僕にとって、「勉強で評価されること」が唯一の居場所を見つける手段でした。
そして気づけば、点数や偏差値を通して「誰に勝った」「誰より下だった」と、周りと自分を比べることが日常になっていました。
幸いにも第一志望の大学には合格できたけれど、大学生活が始まってからも比較癖は消えるどころか、より強くなっていきました。
「この人は将来有望そうだな」「あの子は人間関係も順調そう」——そんな風に周囲の輝きと自分を照らし合わせては、自分だけが取り残されているような気持ちになっていたんです。
とくにSNSを見るたびに、友達のリア充報告やインターンなど、自分より“先に進んでいるように見える誰か”の姿に心がざわつき、次第にその友達さえも避けるようになりました。
でもあるとき、「なんで自分はこんなに人と比べてしまうんだろう?」と、責めるのではなく問い直すことで、少しずつ自分の心の癖が見えてきたんです。
同じように、「人と比べて苦しい」と感じる人はきっと多いはず。
だからこそまずは、そもそもなぜ人は他人と比べてしまうのか?
その心理的な背景を丁寧に見つめ直すことが、抜け出す第一歩になるのではないでしょうか。
この記事では、「人と比較してしまう癖」の原因と悪影響、そして僕自身の経験談も交えた向き合い方を紹介します。
特に、SNS時代に生きる20代にとって、自己肯定感を保つことは大きな課題です。
この記事が少しでも「自分らしく生きるヒント」になれば嬉しいです!
なぜ人と比べてしまうのか?|比較の心理と背景
まず最初に、「なぜ私たちは人と比べてしまうのか?」という問いについて考えてみましょう。
人と自分を比べるという行為は、意識的にせよ無意識的にせよ、誰もが一度は経験する心の動きです。
それは、決して珍しいことではなく、ごく自然な心理的反応とも言えます。
しかしその一方で、他人との比較が自分を苦しめたり、モチベーションを下げたり、自己否定につながってしまうことも多いのが現実です。
そこで大切なのは、「人と比べてしまう自分」を責めるのではなく、その背景にある心理や原因をしっかりと理解し、自分の心の癖に気づくこと。
ここでは、私たちが人と自分を比較してしまうとき、心の中でどんな感情や価値観が働いているのか、主な原因を整理しながら掘り下げていきたいと思います。
自信がない
自分に対して「これでいいんだ」と思える自信がないと、私たちはどうしても他人の評価や成果を“自分の価値のものさし”にしてしまいがちです。
たとえば、SNSで「就活で内定をもらった」「資格に合格した」という投稿を見たとき、「自分は何も成果を出せていない」と感じることはありませんか?
それは、自分の存在価値が揺らいでいるサインかもしれません。
本来、私たちの価値は他人と比べなくても存在しているはず。
でも自信がないと、その「自分の基準」を信じることができず、つい他人の成功や称賛を基準にしてしまうのです。

承認欲求が強い
人間には根本的に「誰かに認められたい」という承認欲求があります。
それは決して悪いことではありません。
しかし、それが強すぎると、「他人にどう思われているか」を過度に気にするようになり、常に比較の対象が外部にある状態になります。
「すごいね」「偉いね」と言われたいがために、他人と張り合ったり、自分をよく見せようと無理をしてしまうことも。
この承認欲求が満たされないと、自分の価値に対する不安感がさらに強まり、比較のスパイラルに陥る可能性もあります。

勝ち負け思考
「勝つこと=正義、負けること=ダメ」という価値観に染まっていると、私たちはあらゆる場面で無意識に優劣をつけてしまう癖がついてしまいます。
誰かが成功すれば、「自分は負けた」と感じてしまう。
人と違う道を選んだとき、「この選択は正しかったのか」と不安になる。
これは、人生そのものを「競争」として捉えてしまう勝ち負け思考の影響です。
この思考が強いと、たとえ今の自分に満足していても、「もっと上がいる」と思ってしまい、永遠に満たされない感覚に苦しむことになります。

優柔不断な性格
自分自身の価値観や判断基準がしっかりと定まっていないと、人の意見や行動に簡単に影響を受けやすくなります。
たとえば、「周りがみんな就職活動を始めたから、自分も焦って始めなきゃ」といった行動は、自分軸ではなく他人軸で生きている証拠。
優柔不断で流されやすい人ほど、「人と比べては落ち込み、またそれに引っ張られて動く」という負のループに陥りやすいのです。

以上が他人と比べてしまうことの主な原因です!
多くの方はどれかに当てはまると思いますが、皆さんはどの要因で比較癖があるかわかりました?
ちなみに僕は全部当てはまりました。。。。(´;ω;`)
もちろん、こういう原因を深ぼっていけば外部要因(家庭、学校の環境)などによるものも大きいとは思いますが、しっかり自分と向き合うことは今後生きていくうえでも自分の考え方、行動の傾向を知ることができるのでぜひ早めにやっておきましょう!
人と比較することのデメリットとは?
人と比べることそのものが悪いわけではありません。
ときには刺激をもらったり、「自分も頑張ろう」と前向きな気持ちになれたりすることもあります。
ですが、その比較が過剰になったり、無意識のうちに「自分を下げる材料」になってしまうと、さまざまな悪影響を引き起こします。
ここでは、僕自身の体験も交えながら、特に注意したいデメリットを3つに絞ってお伝えします。

自己肯定感が低下し、自分の価値がわからなくなる
人と比べ続けていると、どうしても「自分にはあれがない」「あの人はすごいけど、自分は何もできていない」といった思考に陥りやすくなります。
こうした思考が続くと、本来の自分の強みや魅力が見えなくなってしまい、自分の存在そのものを肯定できなくなるのです。
僕も以前は、「自分は大した経験も実績もない」と思い込んで、挑戦することすら怖くなっていました。
SNSで人のキラキラした投稿、うらやましい状況を見るたびに、自分との差に落ち込み、自信を失っていく
——そんな負のスパイラルに何度も陥りました。
常に「足りない」と感じ、焦りや不安に追われる
比較を繰り返すことで、どれだけ頑張っても「まだ上がいる」「自分はもっとやらなきゃ」という終わりのない焦燥感が生まれます。
それはまるで、自分に対する「無言のダメ出し」が続いているような感覚です。
この状態が続くと、心が休まる瞬間がなくなり、どんどん疲弊していきます。
小さな成功すら素直に喜べなくなり、人生そのものに満足できなくなることも。
僕自身、大学生活の中で「周りの誰かがすごいことをしている」と聞くたびに、「自分は遅れている」と感じ、根拠のない焦りに駆られていました。
その結果、本来自分がやりたいことや、ゆっくり向き合うべき時間さえも見失っていたように思います(´;ω;`)
他人の人生を生きようとして、自分をすり減らしてしまう
比較に支配されていると、自分の本音よりも「どう見られるか」「どう評価されるか」が優先されてしまいがちです。
すると、知らず知らずのうちに「他人の価値観」で生きるようになってしまいます。
たとえば、「みんながインターンしてるから自分も行かなきゃ」「あの子は彼氏がいるのに、自分は…」といったように、誰かの人生と自分を照らし合わせることで、自分本来の意思が曖昧になっていく。
僕も当時、自分の選択やペースに自信が持てず、何かと「これで合っているのかな?」と人の目を気にしていました。
でも今思えば、その多くは他人の人生に自分を合わせようと無理をしていただけだったと思えるようになりました。
実践的な対処法|比較の癖から抜け出すためにできること
では、人と比べてしまう癖から抜け出すには、具体的にどんな行動をとればいいのでしょうか?
僕自身、ずっと比較に苦しんできた経験がありますが、以下の3つの方法を意識するようになってから、少しずつ心が軽くなっていきました。
どれも特別なスキルや道具はいらない、誰でも今日から実践できる方法です。

SNSから距離を置く
人と比べて落ち込む原因のひとつに、「見なくていい情報を見てしまうこと」があります。特にSNSは、自分よりキラキラして見える他人の投稿であふれていて、比較のトリガーになりやすいツールです。
僕はある時期、Instagramを開くたびに友人の起業報告やインターンの実績、海外旅行の投稿などに心をかき乱され、「なんで自分はこうなれないんだろう」と落ち込んでばかりいました。
そこで思い切ってアプリを一時削除し、代わりに読書や散歩、日記の時間を増やしてみたんです。すると、外からの情報が減ることで、自分の心の声が少しずつ聞こえるようになった気がしました。
SNSを完全にやめる必要はありませんが、「見ない時間を意識的に作る」ことだけでも、心の安定に大きな効果があります。
他人ではなく「過去の自分」と比べる
他人と比べるクセがついている人は、自分の成果や努力に鈍感になってしまいがちです。
でも、昨日の自分と今日の自分を比べて、小さな変化や成長を見つけることができれば、自己肯定感は自然と育っていきます。
僕は毎晩、「今日自分が少しでも頑張れたこと」を1つ書き出す習慣を始めました。
たとえば、「午前中しっかり集中できた」とか、「苦手な人と話せた」とか、ほんの些細なことでいいんです。
それを続けているうちに、「自分だって、ちゃんと進んでいるじゃないか」と思えるようになってきました。
他人は他人、自分は自分。成長の物差しを外に置くのではなく、自分の中に置くことが、比較の癖を和らげる大きな一歩になります。
自分の価値を「相対」ではなく「絶対」で見る
私たちはつい、他人と比べて自分の良し悪しを決めてしまいがちです。
でも本来、人の価値は「誰かより優れているかどうか」ではなく、その人がその人らしくあること自体に意味があるはずです。
たとえば、要領が悪くてもコツコツ頑張れること、派手ではなくても周りを丁寧に支えられること、うまく話せなくても人の話を親身に聞けること。そういった一見“目立たない”強みは、比較していると見落としてしまいます。
僕も以前は、「人前でうまく話せない自分は劣っている」と感じていました。でも、自分が文章で気持ちを表現できることや、1人でコツコツ考えることが得意だと気づいたとき、「自分にしかない良さ」が確かにあるんだと思えるようになったんです。
他人の価値に目を向けるばかりではなく、「自分だけが持つ絶対的な価値」に目を向ける習慣をつけること。
それが、比較から自由になるための鍵だと思います。
根本的な解決法|「他人軸」から「自分軸」へ
僕がいろんな対処法を試して、少しずつ自分の心と向き合っていくなかで、ようやくたどり着いたひとつの結論があります。
それは、「他人軸で生きるのではなく、自分軸で生きることが大切だ」ということ。
他人の価値観や評価、成功のペースに合わせて生きようとすればするほど、自分の心はどんどん苦しくなっていきました。
どんなに頑張っても「誰かと比べて劣っている気がする」「自分は遅れている」という感覚が拭えず、常に不安と焦りがつきまとっていたんです。
でも、ふと立ち止まって考えてみたんです。
「自分は、本当はどうしたいんだろう?」
「周りにどう見られたいか、じゃなくて、自分が納得できる生き方ってなんだろう?」
そうやって自分の内側にある「本音の声」に耳を傾ける習慣を持つようになってから、少しずつ他人の目が気にならなくなってきました。
たとえば、
「この分野に興味があるからやってみたい」
「これは人がどう思おうと、自分にとって大切な価値観だ」
そう思えるものを自分の中に見つけて、選択や行動の基準にしていくことで、ようやく「自分の人生を自分で生きている」という実感が持てるようになったんです。
もちろん、最初から明確な“自分軸”がある人なんて、そう多くはありません。
僕自身、何度も揺れたり迷ったりしてきました。でも、それでいいと思うんです。
大事なのは、誰かと同じであることでも、完璧な自分を作ることでもなくて、「不完全でも、自分を大切にしよう」と決めること。
理想通りに進めなくても、「今の自分にOKを出してあげる力」こそが、本当の意味での自己肯定感なんだと感じています。
人と比べてしまうのは、ある意味“誰かの人生を生きようとしている状態”とも言えます。
でも、あなたの人生を生きられるのは、あなただけです。
他人の期待や基準に合わせる人生ではなく、自分の価値観を軸にした人生を選ぶこと。
それが、比較の苦しみから少しずつ解放され、心が穏やかに満たされていくための、根本的な解決策だと思います。
まとめ
人と比較してしまうのは、人間としてとても自然なことです。
誰かの頑張りや成功を見て焦ったり、落ち込んだりするのは、それだけ「自分も何かを成し遂げたい」と思っている証でもあります。
でも、その比較が日常になりすぎて、自分の心を傷つけるようになってしまったら
——それは「生き方を見直すタイミング」なのかもしれません。
人と比べては落ち込んでしまう。
何をしても満たされない。
もっと頑張らなきゃと思うのに、空回りばかりしてしまう。
そんなときは、ほんの少しだけ立ち止まってみてほしいのです。
自分を大切に。